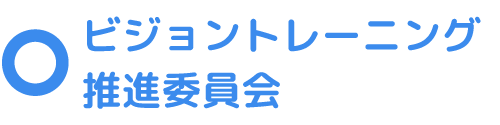岸 浩児(ビジョントレーニング推進委員会 委員長)インタビュー
岸 浩児
現在の日本におけるビジョントレーニングは少しずつ認知度は高まってきており、その中で理論的な事はある程度発信されていますが、「それをどのように実践するのか?」についての情報は、まだまだ不足しているのではないか?というのが現場で指導している多くの皆様の見解です。
認定講座の内容をキチンと押さえベースの部分を構築して初めて「学習」や「スポーツ」などでの具体的な成果、という話になるのだと思います。まず成果ありきではなく「どのように土台を作り、その上に何を建てるか?」という事だと思います。
お越しいただく方には現時点でのご自身なりの疑問点や課題などもぜひお持ちいただければ、それにキチンとお応えできるような流れにしていきたい、とも思っています。皆さんが現場で困っている事に対して今までの自分の経験を通してお伝えしていきたいと思います。
2019年の振り返り
ー 2019年よりそれまでの「勉強会」という形から、指導者としてのノウハウをお伝えする「ビジョントレーニング指導者資格認定講座」にバージョンアップし開催をさせていただきました。講座の開催によりさまざまなノウハウが開示され、多くの指導者が現場指導に取り組める環境がかなり推進されたと思いますが、いかがでしょうか?
岸 初めての方は2級講座からスタートされるわけですが参加してくださる方とのコミュニケーションの中で強く感じたのは「まだまだビジョントレーニングは世間には知られていないんだな」ということです。
ー 詳しくお聞かせください。
岸 もちろんビジョントレーニングの認知度自体はさまざまな先生方の出版やスポーツ界での導入事例などを中心に上がってきているとは思います。ただ実際には「ビジョントレーニング」という言葉だけが独り歩きし内容はほとんど伝わっていないんだな、というのが正直な感想ですね。
ー そうなんですね。
岸 例えば「とにかく眼を動かせばいい」とか「動体視力を鍛える」という部分だけにフォーカスされてしまっているように感じます。じゃあ動体視力って何?ときくと「動いているものを早く認識する」という程度で、もちろんそれは間違いではないんですが、それだけで終わっている指導者の方も多く「もっともっと大事なベースの部分があるのに・・」と思ってしまう事も多々あります。
ー はい。
岸 そういう意味で「認知度が上がる」のは大歓迎ですが同時に「認識を深める」ということを意識して行かないと、なかなかトレーニングを本当に必要としている人に伝わって行かないんだろうな、という事が改めてわかった1年でした。
ー 我々が提供している講座は「2級・1級・インストラクター」とあり、それぞれの講座に目的があります。そして入り口である2級講座にご参加いただく方の構成比としては概ね「学校教員・放課後等デイサービス職員・保護者」など「お子さんのためのトレーニング」を目的としている方が80%、あとスポーツや一般、シニアなど所謂「大人のためのトレーニング」を目的としている人が20%というような内容でした。
岸 そうですね。
ビジョントレーニング推進委員会が目指すトレーニングの理念
ー そういう意味では現在、MWT協会ビジョントレーニング推進委員会が提案しているビジョントレーニング講座は「子どもからアスリート、一般、シニアまで」の全ての層の方々に理解~実践していただくためのノウハウですが、ビジョンとはいうものの「目」だけではなく「体も含めた全体のバランスを整える」という要素も強いわけですね!
岸 そうですね。ビジョントレーニングの定義として言われているように「人間の入力~思考~出力のサイクル全体を活性化する」という意味でいうと当然目だけではなく体や考え方なども含めたものなので「アイトレーニング」などという狭い範囲で捉える事はとてももったいないし本質ではないと思います。
ー はい。
岸 現場で指導される方には、トレーニングを指導し実践された方がトレーニングにより良くなっても悪くなっても、その結果全てが「エビデンス」だよ、ということをお伝えしたいです。「第三者的な評価」というのは正直あまり役にたたないです。起こっている事に意味があると思います。きちんとトレーニングをされる方に向き合って「これがいい」と思う取り組みを提供したのであれば、かならず良い方向にいくはずなので一喜一憂せずに自信を持って長い目で堂々と指導をしてほしいと思います。
ー なるほど。
岸 例えばある取り組みを実施して思うような結果が出なかった場合、それは「また別の結果」になっているわけですよね。
ー はい。
岸 であれば「こういう風にしたらこういう結果になるんだ」という別のルートを見つける事ができたという風にも言えるわけです。実際「両眼視」のトレーニングを行ったからと言って「両眼視」という部分だけで結果がでるわけではなく、副次的に別の結果にもつながるケースも多々あるわけです。
ー そうですね。
岸 そこを指導者が「1+1=2」みたいに限定する必要はないのかなと。相乗効果により「1+1=50」(笑)になることもありますよ。なので結果に囚われずその人にとって良いと思った取り組みに自信を持って指導すればいいと思います。それが結果として、その人たちのためになると思います。
ー 「固定概念を外す」という事でしょうか?
岸 そうです。最初はマニュアル通りにしかやれないでしょうが、経験を積むことで「その人に一番必要な取り組みは何か?」が見えてくるはずです。なのに一律にマニュアル通りにしかやらない、というのは指導者の怠慢です(笑)必要に応じて変えるべきところは変えないと。
ー そういう意味でビジョントレーニング推進委員会のメンバーは長年に渡り現場で指導に向き合って来られた方々ですが、やはり机上ではなく現場で経験を積み重ねる事でしか得れないものが必ずあるという事ですね。
岸 そうですね。例えばうちの教室にはもう10年以上にわたってずっと通ってくれている人もいますが、その人はトレーニングの成果が出ていないから継続されているわけではなくて当初の目的からどんどん変化~進化して現在に至っているというか更新されていく新たな目的のために通ってくれているわけです。
ー なるほど。フィットネスジムのような感じですね。終わりはないというか。
岸 はい。それは担当トレーナーがその人がその時に必要なトレーニングを提供できるよう、とにかく経験を積み重ね、そこから適切な対応ができるようになったからでもあるわけです。なので内容もさることながら、指導者はとにかく多くの指導経験を積み重ねるという事がとても大事だと思います。
ー インストラクターの方は「量を質に転化させる」という意味でも、ぜひ多くの経験を積むことで素晴らしい指導者になっていただければと思います。
子どもを対象とした受講者の皆さんに感じた事~ できないのではなく「経験不足」だということ
ー では最初にお子さんのためのトレーニングを目的としている方、学校の先生や放課後等デイサービスの職員の方との交流の中で気づかれたことは何かありますか?
岸 (苦笑)正直に言いますと、そういった指導者の方自身のビジョンに問題のあるケースが多いように感じました。偏った目や身体の使い方をしておられ「ぎこちないな」という印象をもったことが多々あります。
ー なるほど。
岸 なので2級講座でお伝えしているように「理論の理解と合わせて自分自身が、しっかりとビジョントレーニングを実践し成果を体感した上で、ご家庭や職場での指導」というのが、やはりとても大事だと思います。まずは指導者の方が成果を体感することには大きな意味があると思いますし、逆にそれがないとそれこそ「絵に描いた餅」のような話になってしまいます。
ー そうですね。ただ参加者の方にお話を伺った際に、先生であれば生徒さん、保護者であればお子さんというか「子どものために」という動機で参加される方がほぼ100%で「自分の事は2の次、3の次」という感じだったように思います。
岸 そうですね。「自分の事よりもまず子どもに・・」という思いも理解しますし何かと忙しい時間をやりくりして講座に参加してくださる教職員の方には頭の下がる思いです。また「現場でどのように対応すればいいのか?」という事に迷いや行き詰りを感じておられる方も多数おられました。「組織としてしなくてはいけない事」と「子どもにしてあげたい事」との間でジレンマを抱えつつ努力しておられる教職員の皆様に何とかお応えしたい、という想いは強くあります。
ー そうですね。
岸 やはり組織では「この子はこうやったらもっともっと伸びるんじゃないか?」というよりは、最初から枠を決めて「この子たちはこれぐらいが限界だろう」という見方、あるいは対応の仕方になってしまうのだと思うのですが、「やれば必ず変わる。できないのは経験が不足しているだけなんですよ」ということをお伝えしていますし、講座に参加されビジョントレーニングを現場で子どもたちに向け実践された方はそれを必ず実感されているはずです。
ー 子どもに関わる方からは「グレーゾーン」という言葉が何かにつけてよく出てきますね。
岸 もちろん現代の環境の中でさまざまな課題が多く見受けられるのも事実です。ただ教室にお越しになられる方のお話を聞くと「いろんな種類の検査方法が増えたが故に、今までは特に問題とされていなかった子どももそこに含まれるようになり、結果として保護者の方がより不安を感じている」というケースがとても多いように感じます。先日もある機関で検査を受けたら「重度の自閉症」だと診断され悩んでおられる方がお越しになられました。
ー 岸先生から見てその子はどんな状況だったのでしょうか?
岸 確かにコミュニケーションは取りづらいけども会話は成立しているし、「こんな取り組みをしよう!」と提案するとちゃんとやってくれます。全体的に観た場合、対人関係に課題があるというだけで、そこまで問題があるの?と感じているのが正直なところです。
ー なるほど。
岸 最初は同じクラスの子ども達とは離れた場所でひとりぽつんとプリントなどをやっていましたが、今は普通にみんなと一緒にトレーニングもしているし、単に最初のコミュニケーションのきっかけを作るのが苦手なだけで、そんな子は昔からそれなりにはいましたよ。
ー 確かに。
岸 でも重度の自閉症と言われたら保護者はもちろん本人もなんとなくニュアンスを感じて落ち込みます。実際にそれまでは毎週教室に来てトレーニングを楽しそうにやっていた子が、ある日凄く落ち込んだ状態で教室に来たのでお母さんに確認してみると「検査をしたら重度の自閉症と言われました」ということでした。でも何をもって自閉症と判断されているのかの基準が正直よくわからないです。
ー そうですね。
岸 そういう意味で結果として、いろんな検査が良くない方向に作用しているように思えて仕方がないです。中には普通にしつけレベルでできる改善点を「うちの子は発達障害だから仕方ないんです」と単に放置している保護者の方もおられます。まあうちの教室では子どもは一律公平な立場で「悪い事は悪い、良い事は良い」と特別扱いはしないので「厳しい」と思われているかもしれませんが(笑)クラスのみんなとどのようにコミュニケーションするかを学ぶのも大事な事なので、そこはキチンとしています。(笑)
ー さまざまな検査も含めて、いろんな情報に翻弄されて不安になり子どもにとって本当に今何が必要なのか?ということが見えにくくなってしまっているんでしょうが、大事なのは「子どもの力を信じる」という事なんでしょうね。
ー (笑)昭和っぽいですが大事な事です。
岸 その通りです。
岸 (笑)「うちの子はじっとしていられないんですよ」と保護者の方は何の気なしに高をくくっておられても実際にトレーニングをしていくうちに、きちんとクラスのみんなと一緒に取り組みをできるようになってきます。
一般、アスリートの方を対象とした受講者の 皆さんに感じた事
ー 一般やアスリートの方への指導目的でお越しになられた方はいかがでしたか?
岸 学校の先生などでスポーツに関わっておられる方などは体の動きはスムースだがビジョンは使えてない、という方が多いですね。
ー なるほど。
岸 やはり「自分でトレーニングしてみたい!」という興味を持ってご参加いただいた方は、まあ当たり前と言えば当たり前ですが、どんどん成果を出されますし、その上で現場指導にも上手に繋げられていると思います。アスリートの方などは「えっこんな事だけでこんなに変わるんだ!」という風にびっくりされます。ほとんどのアスリートは「ビジョントレーニングはもっと複雑なトレーニング」だと思っていたようです。
ー なるほど。
岸 例えば私が指導してきたプロアスリートでも、ビックリするくらい目が使えていない方が多いです。そこそこ使えていたのは2人くらいかな?(笑)逆に言うと「ようそんな状態でプロになれたな!」という感じです(笑)
ー (笑)そうなんですね。
岸 特にアスリートは取り組む競技の特性によって良くも悪くもクセが強く目も体もバランスが良くない方は多いです。なので、シンプルな取り組みを実施するだけで大きく変化しますし、また良くも悪くもアスリートは「競技の結果に出る」という意味でフィードバックも早いので、結果が出れば特にこちらが何も言わなくても、より積極的に取り組むようになりますね。
ー プロアスリートなどは最初からできている人が多いのかな?という印象もあるかも知れないですが、そうではないんですね?
岸 その通りです。「この人ビジョントレーニングをしたらもっともっと伸びるのにな」と思うプロ選手がいろんなジャンルにたくさんいます(笑)
ー そういう意味では子どもにしろプロアスリートにしろ「最初はできていない」という状態がほとんどなんですね。
岸 そうですね。ベーシックな部分は子どもの頃に学べる仕組みがあれば、いろんな意味で良化して行くでしょうね。
ー そういう意味でも「一般の方々に認識を広め深める」のが大事ですね。アスリートではなく一般社会人においても今の時代「情報処理能力」が問われますし、テクノストレスなどを抱える方も多いわけですから。
岸 最初は同じクラスの子ども達とは離れた場所でひとりぽつんとプリントなどをやっていましたが、今は普通にみんなと一緒にトレーニングもしているし、単に最初のコミュニケーションのきっかけを作るのが苦手なだけで、そんな子は昔からそれなりにはいましたよ。
ー 確かに。
岸 でも重度の自閉症と言われたら保護者はもちろん本人もなんとなくニュアンスを感じて落ち込みます。実際にそれまでは毎週教室に来てトレーニングを楽しそうにやっていた子が、ある日凄く落ち込んだ状態で教室に来たのでお母さんに確認してみると「検査をしたら重度の自閉症と言われました」ということでした。でも何をもって自閉症と判断されているのかの基準が正直よくわからないです。
ー そうですね。
岸 そういう意味で結果として、いろんな検査が良くない方向に作用しているように思えて仕方がないです。中には普通にしつけレベルでできる改善点を「うちの子は発達障害だから仕方ないんです」と単に放置している保護者の方もおられます。まあうちの教室では子どもは一律公平な立場で「悪い事は悪い、良い事は良い」と特別扱いはしないので「厳しい」と思われているかもしれませんが(笑)クラスのみんなとどのようにコミュニケーションするかを学ぶのも大事な事なので、そこはキチンとしています。(笑)
ー (笑)昭和っぽいですが大事な事です。
岸 (笑)「うちの子はじっとしていられないんですよ」と保護者の方は何の気なしに高をくくっておられても実際にトレーニングをしていくうちに、きちんとクラスのみんなと一緒に取り組みをできるようになってきます。
ー さまざまな検査も含めて、いろんな情報に翻弄されて不安になり子どもにとって本当に今何が必要なのか?ということが見えにくくなってしまっているんでしょうが、大事なのは「子どもの力を信じる」という事なんでしょうね。
岸 その通りです。
VT1級・インストラクター資格者の 皆さんへのメッセージ
ー 2019年に1級もしくはインストラクター資格を取得された1~3期生の方が現場で指導をスタートされる、その多くが2020年からになると思います。今後、皆様とは継続的にWEBミーティングや研究会などで情報共有や意見交換を行っていく事と思いますが、まずは1級資格を取得された方々へのメッセージをお願いします。
岸 そうですね。1級資格の目的は「一般の方に向けてのトレーニング指導とビジョンチェックを含む『体験会』を実施できるノウハウ」をお伝えしました。ぜひ皆さんには「ビジョントレーニングとは何なのか?」ご理解いただくための機会として体験会をそれぞれの地域、コミュニティにおいて開催していただき、トレーニングを必要としている方に実践していただく事の出来る機会を創っていただきたいですね。
ー なるほど。
岸 トレーニングが上手く行かなかった場合の改善にむける、というのはもちろんですが、上手く行った場合も「良かったね!」だけで終わるのではなく同時に「なんでよくなったのか?」についてまずは自分なりの推測でもいいので分析し小さな把握を指導者の方が積み上げていく事で、よりトレーニングの可能性が高まって行くように思います。
ー またそれを指導者勉強会や研究会で共有し高めていくという事も含めてですね?
岸 その通りです。現場のいろんな事例がトレーニングの質を高めるために一番必要な要素です。そもそもビジョン=脳の事なので仮説はたくさんありますが、実際にはまだまだ分かっていない事の方が多いわけです。
ー 科学的な根拠や裏付けはもちろん大事ですが、そこに縛られて結果的にトレーニング自体が小さなものなってしまっては意味がないというか・・
岸 そういう事だと思います。でなければ巷にある本やマニュアルだけで指導が成立しますし誰も困る人などいないはずですが現実はそうではないです。だから多くの方が指導者講座にもお越しいただいているわけですし。
ー その通りです。
岸 いずれにしても現場は毎日いろんな試行錯誤の繰り返しです。でもその現実的な対応策が見えないと結果的に社会的な認識も広がって行かないというか、ある一部の固定した認識というか理屈だけが拡がって行くような事になると思います。
ー そうですね。
岸 そういう意味でも資格を取得された方はぜひ講座の再受講も可能な範囲でぜひお願いしたいです。講座を初めて受講された時の自分と、その後実際に指導をされた上での自分は同じ自分でもまったく受け取り方が異なっているはずです。何度も学ぶことで過去に受講し理解できていたと思っていた部分が認識できていなかったり、さらに補強できたりと得るものはかなり大きいはずです。
ー 気づきのレベルも更新されているわけですから。
岸 はい。もちろん自分も含め指導者の方の学びに終わりはないです。常に学び続けることで自分が提供できるトレーニングと、それに付随する成果や喜びの質と量も大きくなっていくと思います。
これからビジョントレーニングに取り組んでみたい 方に向けてのメッセージ
ー それでは最後にこれからビジョントレーニングに取り組んでみたい方に向けてのメッセージをお願い致します。
岸 自分の中では今までの講座においては最大限でお伝えしてきたつもりですが、その経験も含め自分の学びをフィードバックさせ、2020年はさらに「濃い講座」をお届けできると思います。
ー さらに濃い?(笑)
岸 はい(笑)今までお伝えした内容をより細かに理解していただけるよう新たな自分の学びも加えて再構築し続けていますので、ぜひ足をお運びいただければと思います。現在指導する立場の方も、必ずしもそうではない方もいろんな意味において自分に起こってきた、さまざまな事柄「なぜああいう風になったんだろう?」というような事がビジョンやメンタルトレーニングの理解~実践を通じて理解できるようになると思います。それはご自身の今後の人生において大きなプラスになると思います。間違いなく自分自身もそうでしたし。
ビジョントレーニング推進委員会の新企画 「発達支援のためのビジョントレーニング集中講座」 について
ー 2020年よりスタート予定の新企画についても少しお願いします。
岸 新たにスタートする「発達支援のためのビジョントレーニング集中講座」は、今まで開催してきた講座で資格を取得された方へのフォローにもなり、またこれから新たに子どもの発達に向けてのビジョントレーニングを学びたい方の入り口にもなる機会にできればと思い起案しました。
ー なるほど。
岸 講師を担当していただく松本加寿美さんは第12号の機関誌のインタビューにもあったように学校の発達支援の現場で長年に渡り指導し試行錯誤を繰り返す中で我々のビジョン指導者講座に辿り着かれ即時全ての資格を取得され、またメンタルや脳波についても現在進行形で学ばれ、「発達支援」というフィールドに還元し子ども達やその保護者の方にお伝えされています。
ー はい。
岸 私が指導者講座でお伝えしている内容はいわば全般的な内容であり、もちろん発達支援に関連する内容もお伝えはしているのですが、まだまだお伝えしきれていない事もたくさんあります。そういう意味で松本さんにおいてはご自身の経験にビジョントレーニングをミックスして私の講座ではフォローしきれていない発達支援に関するノウハウを伝えていただけると思います。
ー そうですね。
岸 なので発達支援=お子さんに関わられている方は資格をお持ちの方であれ全くこれから学ばれる方であれ、ぜひご参加いただければと思います。発達支援の現場で深くまた積極的にいろんな事を取り入れて指導されている松本さんの講座は必ず役に立つというか「役に立たないわけがない」と思うので(笑)現状の指導者講座と合わせてぜひお役立ていただければと思います。
ー 今後さらに今回の発達支援と合わせ「アスリートのためのビジョン」や「一般」「シニア」の方など、対象を絞った講座の構築なども含めビジョントレーニング推進委員会で検討して行くとのことですが、まずは2020年もよろしくお願い致します。
岸 死なん程度にがんばります(笑)
ー (笑)ありがとうございます。